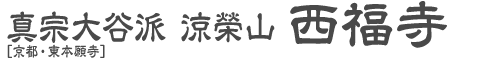今回は11月3日(日)の当山報恩講を前にして、報恩講の意味についてのお話でした。報恩講とは 一言で言えば親鸞聖人のご法事です。「報恩」とは、自分が受けた恩に報いることであり、「講」とは、皆で集い語り合うことです。親鸞聖人のご恩に報いる為に行われる法会なのです。
では、どんなご恩をいただいたのでしょうか。親鸞聖人は本願念仏に遇われ本願念仏の世界に生きられました。お念仏、南無阿弥陀仏が生活の根本である、私が生きていく上での土台はお念仏、南無阿弥陀仏より他にないことを顕らかにされました。他を土台にしても生きていけると思われますか?人間が考えたもの、作ったものを当てにするとどうなるでしょう?うまくいっている時は良いでしょうが、都合が悪くなったり、うまくいかなくなるとたちまちダメになり、苦しみます。例えば 健康であることを当てにする場合、努力して健康でいられる時は良いですが、事故にあったり病に襲われたらどうですか?それに人間は老いるものですし。財力だってあるほうが良いかも知れませんが、土台にはなりませんよね。
どんな人にもどんなことがあっても揺るがない中心軸、それはお念仏一つでよいのです。そのことを顕らかにしてくださった親鸞聖人のご恩に報恩講を通して気づきましょう、報いましょう。報恩講は私たち一人一人のために行われるのです。
********
御門徒の皆様へ
来る11月3日(日) 西福寺報恩講を厳修いたします。万障繰り合わせの上、お越しください。お待ちしています。
(筆・坊守 釋尼育英)