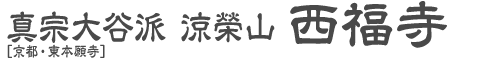来月11月3日に報恩講を迎えます。報恩講とは一言で言うと宗祖親鸞聖人のご法事です。「講」とは集まって聞法するという意味です。宗祖のご命日(11月28日)を期して、真宗寺院では毎年必ず厳修されます。宗祖が顕らかにされた真実の教えを聞信する為にです。宗祖はご自身を含め私たち人間は「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」といただき、そんな私たちでも救われる手立てを伝えてくださいました。
報恩講という、特別な浄土の荘厳をして、特別なお勤め(正信偈真四句目下げや念仏和讃淘五)をして、講師の先生のお話を聞く、そういった特別な場が開かれます。私たちが報恩講の準備をし、開催するその前にそれに先立って宗祖からの促しがあります。私たち真宗門徒にとって報恩講とは、宗祖がいただいた大切な浄土の教えを聞信し、私たちの生活の土台、拠りどころ(宗)を明らかにする大切なご法事です。皆さん、どうぞ 11月3日の報恩講においでくださいませ。
(筆・坊守 釋尼育英)