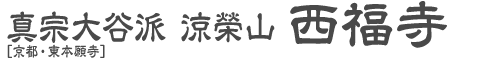1月31日に前進座による「花こぶし」を観劇しました。今回は 親鸞聖人関東布教時代の有名なエピソードの一つである「山伏弁円の回心」に触れました。その当時 筑波山の修験者を束ねていた弁円は、人々が親鸞聖人のお念仏に惹かれて山伏弁円らの修験道から遠ざかっていくことに腹を立て、祈禱や呪法で聖人を亡き者にしようとしました。そんな弁円を親鸞聖人は受け入れ、共に念仏をとなえながら歩もうと諭し、弁円は感動して回心したのです。
弁円の姿から、「人事を尽くして天命を待つ」と「天命に安んじて人事を尽くす」という表現を思い起こし、考えてみました。前者は世間でもよく聞きますね。自分の思いで努力してできるだけの事をして、後は天の命を待つ。天の命とは何でしょうか?人間の力の及ばない何か大きな力、ということでしょうか?でも本当に天の命を待てますか?思い通りの結果が得られたときはよいですが、そうじゃなかったら、どうでしょうか?果たして愚痴はでないと思いますか?
真宗では、後者です。一見似て見えるように思われるかもしれませんが、意味は全く違います。この場合、天命=本願です。自分の思いではないのです。本願に包まれて、安心して力を尽くす。そして結果がどうであれ、事実を引き受ける事ができる。そんな生活態度でいられたら、どんなに楽でしょうか。
(筆・釋尼育英)